
「歩行者相手に交通事故を起こしてしまったら、100%車が悪い」……このような話を聞いたことはありませんか?しかし、それは過失割合ということをまったく理解していない人の言い分です。
確かに、歩行者は交通弱者とされ、法によって守られています。また、運転者は充分な配慮を以て運転をすることが義務づけられています。しかし、だからといって常に歩行者の過失が問われないというわけではありません。
また、車同士の事故でも、当然お互いにどれだけ過失があるかという過失割合によって賠償金が決まってきます。
事故の際100%車が悪いということはほとんどない?
例えば、青信号で横断歩道を渡っている歩行者を、赤信号で進入してきた車がはねてしまったら、申し開きの余地なく100%運転者側の過失となります。
しかし、この時歩行者側の信号が黄色や赤だったり、渡ろうとしたのが横断歩道上でなかったりしたらどうでしょうか。歩行者側にも過失ありとみなされ、その度合いによって「7対3」や「5対5」のように当事者間で損害賠償責任を負うことになります。これを過失割合(責任割合)といいます。
過去の判例を基に決定される過失割合
では、交通事故の過失割合はどのように決めるのでしょうか。
もちろん当事者が話し合って、というわけにはいきません。それぞれが加入している自動車保険会社の担当者同士によって決められます。その際に根拠となるのが過去の交通事故裁判の判例集です。
ありとあらゆる交通事故のパターンが載っており、担当者は類似した事故の判例を基に、妥当と思われる過失割合を決定するのです。
その結果、過失割合の多い方が加害者、少ない方が被害者となります。ただし、事故に関するさまざまな要素も考慮した上で判定されますので、同じような交通事故でもまったく同じ過失割合になるとは限りません。
また、公平性を保つために過失割合の値を修正する「修正要素」もあります。車同士の事故で、一方が大型車、もう一方が軽自動車であった場合や、一方が明らかな脇見運転であった場合などです。
こちらも参考になります「車両保険の免責金額の仕組みについて知っておきましょう」
警察には必ず連絡しよう
交通事故の過失割合を決める際に、双方の言い分が食い違い、難航することがあります。そんな時に根拠の一つとなるのが実況見分調書です。
「事故を起こしたら、必ず警察に連絡する」とされているのは、この実況見分調書を作成してもらうためです。警察は原則として民事不介入ですので、話し合いなどには一切ノータッチですが、「どのようにして事故が起こったのか?」と現場を見分し、双方に事情聴取を行います。これが決め手となって過失割合が減ることもありますので、決して怠らないようにしましょう。
補償金が削られる?過失相殺
過失割合に関連する「過失相殺」という言葉をご存知でしょうか。簡単に言うと、自分にも過失がある場合、相手の保険会社から支払われる補償金をすべて受け取ることはできないということです。
過失割合が「相手7・自分3」と決定したとします。双方の損害が100万円ずつとすると、相手の保険会社から70万円がもらえると考えがちですが、そうではありません。自分にも過失があるわけですから、相手に30万円を支払う必要があります。この結果、自分がもらえるのは40万円になります。
また、被害者側にも過失がある場合は、治療費や休業損害などを含めた全損害額から過失割合に基づいて相殺が行われますので、計算はもっと複雑になります。
最近は自動車保険会社の多くが専任担当者の他にサポートチームがついて事故処理に当たっています。事故調査士、弁護士、車両鑑定人などによって構成されたサポートチームと連携することによって、早急な解決を目指しています。
また、保険会社は被保険者に対して、支払いに関する情報提供が法律で義務付けられています。支払い基準や支払額、減額になった場合は割合とその理由、支払われない時にも、すべて書面で知らせることになっています。
納得のいかないことは必ず申し立てましょう。
交通事故を起こしてしまった時は、過失がどちらにあろうと、なかなか冷静に対処できないものですが、事故を知らせると「次に何をするべきか」と指示してくれるサービスのある会社もありますので、まずは保険会社に連絡しましょう。
そのためにも、自動車保険会社の担当者の名刺を常に持ち歩いたり、携帯の電話帳に登録するなど、すぐに連絡を取れる状況を整えておくことが必要です。
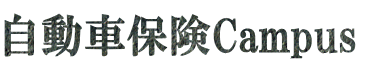
この記事へのコメントはありません。