
自動車保険の保険料は、ノンフリート等級別料率をベースに決められます。契約者はそれぞれ個別の「等級」を持っていて、それに応じて料金が決まる仕組みです。一人の人が2台の車を持っている場合には、それぞれの車ごとに等級は異なります。
等級は契約者個人にもとづくものですので、他人に譲ることはできません。例えば、自分の所有する自動車を友達に売った場合、そのお友達は自分で新たに保険をかけなければなりません。自動車保険は車についているものではなく、契約者についているものです。
事故を起こさないとどんどん割引がよくなる仕組み
等級は1等級から20等級までの20段階に分かれています。通常は初めて自動車保険に加入する場合、6等級からのスタートです。初年度に事故を起こさなければ翌年度は7等級に上がり、保険料の割引を受けられます。その年に事故がなければ次は8等級にと、毎年毎年等級はひとつずつステップアップしていき、割引も大きくなる仕組みです。
最高は20等級ですが、そこまでたどり着くには14年かかります。20等級までいくと、6割以上の割引となります。
事故を起こすと料金は高くなります
事故がなければ割引率はどんどんよくなる一方で、事故を起こしてしまうと等級はダウンし、割引率は下がります。一定レベルのランクまで落ちると、割引ではなく割増しの料率になります。
事故がない場合は毎年1等級ずつアップしますが、事故があると一気に3等級ダウンしてしまいます。つまり、3年分後退するわけです。元の割引率に戻すのには、その後3年間無事故で過ごさなければなりません。
割引はどのくらい違うのか?
ノンフリート等級別料率の仕組みそのものは各社共通ですが、割引・割増率については会社ごとにことなります。そのため、等級が進むとどれだけ安くなるかは一律に述べることはできません。概算での比較となってしまいますが、初年度6等級だったものが翌年度に7等級にアップすると、1割程度保険料が安くなります。
2年~3年無事故で過ごして8等級から11等級になると4割ほど安くなり、9年ほどで15等級になれば5割引きです。20等級になると6割程度の割引となります。事故がなければ保険料はどんどん安くなるのです。
割引率が下がる事故後の3年間
事故を起こしてしまった場合には、3等級ダウンです。今年度が10等級だった場合、翌年度は7等級にまで落ちることになります。事故をして落ちたときの7等級と、6等級の人が無事故で7等級にアップしたときとでは、割引率に差があります。「事故あり」の等級と、「事故なし」の等級は、ランクはおなじでも割引率はことなる仕組みだからです。
事故により等級ダウンした人に適用される割引率の方が低く、「事故なし」の人の割引率と同じものに回復するのには3年間かかります。一度事故をしてしまうと、保険料の面でかなり不利になってしまいます。
安全運転を続けることが一番お得
すべての事故が一律に3等級ダウンというわけではありません。「ノーカウント事故」というものがあり、それに該当する場合は等級ダウンのペナルティはありません。無保険車傷害、人身傷害、搭乗者傷害、代車費用補償特約、弁護士費用等補償特約、ファミリーバイク特約の請求はノーカウントです。
また、対人賠償事故で、対人臨時費用保険金のみの支払いのケース、車両保険で、運搬・納車費用、仮修理費用、盗難車引き取り費用保険金のみの事故の場合にもノーカウントです。
車両保険および身の回り品補償特約で、火災・爆発、盗難、騒じょう・労働争議・台風・竜巻・洪水・高潮、落書き・いたずら、飛来物・落下物などによる事故は1等級だけのダウンとなっています。
自動車保険は、等級がよくなればなるほど保険料が安くなる仕組みです。事故を起こさないことで保険料もお得になりますので、安全運転を心がけましょう。
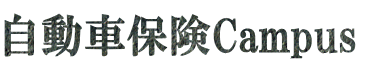
この記事へのコメントはありません。