
愛車が事故でへこんだり傷ついてしまったらショックですよね。新車ならなおさらです。
「でも、自動車保険に入っているし、修理すればいいや」と思っていたところに、保険会社から無情にも「全損なので、○○円までしかお支払いできません」という、少なすぎる補償額の知らせが。直せばまだまだ乗れる状態なのに……。
一体、全損の基準はどのような状態のことを言うのでしょうか。
加入前に条件を確認することが必要
新車をローンで購入した場合や仕事で車を使う人は、車両保険に加入しておいた方がよいでしょう。
車両保険とは、簡単に言うと自分の車が破損した時に、その修理費を補償してくれるものです。任意保険なので、自分で加入する必要があります。
しかし、修理に必要な金額または補償の上限額が100%もらえるとは限らないので、加入前に条件をよく確認することが必要です。
「全損」には二つの意味がある
「全損」というと、もはや原形をとどめないほどにぺっちゃんこ、あるいはベコベコになっている、エンジンがなくなっている、など、凄惨な状態を想像しますね。
しかし、保険会社の定義する全損の基準には2つの意味があります。
一つは一般的に想像される、車体が修復のしようがないほどに壊れてしまっている状態で、「物理的全損」と言います。
もう一つが、「経済的全損」で、修理費が車両の時価と買い替え諸費用を合わせた金額を超える場合にこのように呼びます。
基準となる「時価」はどうやって決めるのか
この時の時価とは、さまざまな項目がありますが、要は同じ車種・型・年代で、使用状況や走行距離も同じくらいの車を中古で買うといくらになるか?ということです。ちなみにこの値段は自動車価格月報(通称・オートガイド)を基準にしています。
これには、売主が車両を下取りに出した場合の買取価格、買い取った業者が他の業者に販売する場合の卸価格、業者が仕入れた車両を整備して店舗で販売する場合の販売価格の3種類が記載されており、このうちの販売価格がいわゆる車両の「時価」になります。
買い替え諸費用とは、事故車両の廃車手続き費用、自動車税及び自賠責保険料、自動車重量税などですが、すべてが賠償の対象となるわけではありません。
例えば、このうち自動車税と自賠責保険料については、「事故と相当因果関係を有する損害」とは認められません。
なぜなら、これらは車両を既に保有していること等によって生ずる費用であり、またどちらも事故によって車両が全損となった場合には、所定の手続きをとることで未経過分を還付してもらうことが出来るからです。
また、自動車重量税は、購入する自動車について自動車検査証の交付等や車両番号の指定を受ける際に、自動車検査証の有効期間や自動車の重量に応じて課せられます。
例え事故にあった車の検査証の有効期間に末経過分があったとしても、自動車税や自賠責保険料のように還付されることはありません。そのため、事故の時点での自動車検査証の有効期間の未経過分に相当する金額は、事故による損害と認められます。
ただし、未経過分の重量税でも、使用済み自動車の再資源化に関する法律(自動車リサイクル法)によって適正に解体され、永久抹消登録の手続き後に還付された分は除外されます。
その他、購入した車両の取得にも費用が発生します。このうち、検査・登録費用及び車庫証明費用は、車両を取得する場合に必要な法定費用(手数料)です。また、これらの代行費用及び納車費用は、車両販売店に対する報酬です。しかし、車両を購入する度に必ず支払わなくてはならないことや、諸手続きも通常販売店が代行するという実情から、これらの費用も買い替え費用に該当するとして、賠償の対象となるとされています。
自損事故を起こして車が壊れてしまった時、「車両保険に入っておけばよかった……」と後悔する人がかなりいるそうですが、こうした条件もよく吟味した上で自分に必要かどうか決めるようにしましょう。
(*ご参考にどうぞ「自動車保険料は新車だと割安になるのをご存知ですか?」)
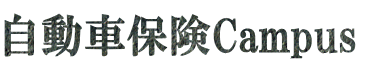
この記事へのコメントはありません。