
自動車保険の保険金がいつ支払われるのかは、自分が被害者であれば特に気になるものです。ケガをして治療費が必要、仕事ができなくて収入が減ってしまうなど、お金に関する心配は尽きません。
しかし、加害者もしくは被害者が保険金の請求をした時は、保険会社は速やかに支払わなくてはなりませんが、示談が長引いたり、特別な調査が必要な場合は、まず請求そのものができません。その間の治療費や生活費は自己負担になります。
そんな交通事故の被害者を救済するために、自動車保険はさまざまな制度を用意しています。
支払期限は法律で決まっている
平成22年4月より施行となった保険法には、「保険給付の履行期」に関する規定が定められています(第21条)。これは、保険給付のための調査期間を経過した場合に保険会社が履行遅滞の責を負うとされるものです。つまり、保険会社は支払期限を策定し、それまでに特別な事情がない限り、保険金を支払わなくてはならないというものです。
多くの保険会社では、「保険金の請求手続きが完了した日を含めて30日以内」としているようです。
生命保険や医療保険とは異なり、相手のあることですから、「最短で5日!」と言うわけにはいきません。実際、各社の支払い実績を見ると、だいたい30日前後かかるようです。
しかし、早急にお金が必要な場合はどうしたらいいのでしょうか。
被害者が請求できる仮渡金と内払金
交通事故の場合、被害者は加害者の加入している会社に対して直接支払い請求を起こすことができます。仮渡金と内払金の二種類があり、このうち内払金に関しては加害者も請求可能です。ちなみに、加害者が請求するには示談が成立していること、加害者が被害者に対して治療費などの賠償金を支払っていることが条件となります。
仮渡金は、賠償金額がなかなか確定しない時に、被害者が治療費などの当座の出費に充てるために一回のみ請求できるものです。請求からおよそ1週間で支払われますが、本請求金額が確定した時点で清算されます。もしも本請求金額より仮渡金の方が多かった時は、その差額を返還する必要があります。
一方、内払金は加害者・被害者の両方が請求できます。事故によってケガを負った被害者が治療継続中のため損害額が算出できない場合でも、その時点で治療費が10万円を超えていれば支払いの対象となります。仮渡金との違いは、120万円を上限として複数回の請求が可能なことです。
診断書や診療報酬明細書(医療機関の窓口で請求すれば発行してくれます)、交通事故証明書などの書類が必要になります。加害者が請求する場合は、治療費などを支払ったことを証明する領収書が不可欠なので、これらの書類は大切に保管しましょう。
内払金は治療が完了(治癒)するか、後遺障害の状態が安定して金額が確定して本請求となった段階で清算となります。
一括払い請求の仕組み
自動車保険には強制と任意があります。強制保険(自賠責)でカバーしきれない分を任意保険で補うことになるわけですが、それでは請求手続きを二回行わなくてはならなくなります。
そこで、任意保険会社が窓口となって自賠責分の支払いも立て替えて行うという便宜が図られています。このおかげで、被害者は一括して給付金を受け取ることができるのです。
示談・和解が成立するまでにはどうしてもある程度の日数がかかるものです。原則30日以内と定められていても、疑わしい点があれば、適切な支払いをするための調査が長引くこともあります。
ですから、はっきり「何日で」とは会社側も明言を避けるでしょう。しかし、当然こうした問題は想定済みであることから、対策もしっかりとられているというわけです。
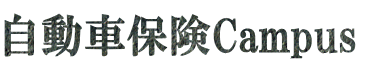
この記事へのコメントはありません。