
自動車保険料は、契約者ごとの等級や運転者の年齢、免許証の色などに加えて、車の種類ごとに決められた「車両料率クラス」によって変わってきます。
たとえば高速で走ることのできるスポーツカーと、家族向けのコンパクトな車では事故の危険度に差がありますので、それに合わせた車両料率クラスが決められているのです。
単に事故の起こる確率だけでなく、盗難のリスクも加味されています。全国的な統計から、よく盗まれる車は料率が高くなる仕組みです。なお、同じ車種でも型式が異なれば料率クラスは異なります。日産スカイラインの中でも、Aという型式の車は「5」なのに、Bという型式は「4」ということがあります。
車両料率クラスの差によって、一番安い車種と一番高い車種では4倍も保険料が違いますので、これはぜひ知っておくべきです。
車両料率クラスとは何か?
車を分類する方法には、メーカー・車種などがありますが、さらに細かく「型式」というものもあります。型式は車検証を確認すれば記載されています。
同じ車種の中でも細かく分類されていて、たとえば、「ANZ10」とか「AX10」というように、アルファベットと数字の組み合わせでできているものです。型式は車のタイプや年式によって違ってきます。
型式別の料率クラスは、「対人賠償」「対物賠償」「搭乗者傷害・人身傷害」「車両保険」のそれぞれごとに決められています。同じ型式でも、対人賠償と対物賠償では料率クラスが異なります。
段階ごとに分けられ料金にも大きな影響がある
車両料率クラスは、1~9までの9段階に分けられており、「1」の保険料が最も安く、「9」が一番高くなっています。損保会社ごとに異なりますが、車両料率クラスが一つ上がるごとに料金はおよそ1.2~1.3倍になります。
「1」と「5」とではおよそ倍の料金の差となり、「1」と「9」とでは4倍の差ができてしまうのです。
例えば車両料率クラス「1」の保険料が2万円の場合、「5」なら4万円、「9」なら8万円となります。かなりの開きがありますので、車を購入する際には、価格だけでなく保険の車両料率クラスも確認した方がよいかも知れません。
こちらも参考にどうぞ「軽自動車は料率クラスがないので自動車保険料がお得になる?」
どのように分けるのか?
型式別の車両料率クラスは、損保会社全社一律で決められています。決めているのは損保会社ではなく、損害保険料率算出機構という組織です。車両料率クラスは、過去の損害率のデータを参考に毎年改定されます。前年度は「5」だった車が今年は「4」になる、「6」になるということがあります。
運がよければ自動車保険料が下がりますし、運が悪いと等級がアップしたのに掛け金が上がってしまうということも起こり得るのです。
損害保険料率算出機構では、毎年の自動車事故のデータを統計的に細かく分析し、事故の起こりやすさを算出しています。たとえば、ある年にある特定の車がよく盗難にあったりすると、その車の型式は翌年に保険料が上がることがあり得るのです。
車両料率クラスが低いということは、全国的に見て、その車・型式に乗っている人の事故率・損害率が低いということです。逆に車両料率クラスが高ければ、その型式の損害率は高いということになります。
どのように確認するのか?
現在、自動車保険に加入している方は、保険証券を見れば確認することができます。保険証券を「発行不要」としている方や紛失してしまった方は損保会社に問い合わせれば、教えてもらえます。
新しく保険に加入する場合には、購入先の自動車ディーラーにたずねればわかりますし、保険加入時に損保会社や代理店に教えてもらうことができます。インターネット上に掲載されていることもあります。ただし、毎年変更されるものですので古いデータではなく、最新のものを確認しましょう。
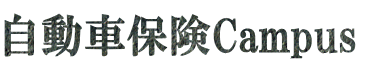
この記事へのコメントはありません。