
示談とは、加害者と被害者が話し合いによって賠償責任の有無やその金額を決定することを言います。交通事故の賠償問題はほとんどが示談で解決しています。
示談交渉は、長らく当事者同士で行うものとされてきましたが、専門知識が必要なこと、感情的になりすぎることなどで難航することが多いため、最近では保険会社の示談担当者が代行することがほとんどです。
しかし、自動車保険に入っていれば示談交渉を無条件にやってくれるわけではありません。
任意保険には7種類ある
自賠責保険に入っていない車は、運転することができません。しかし、その補償額は等級によって決められるため、足りないことがあります。そこで任意の自動車保険で補うことになるわけですが、大きく分けて対人賠償保険や対物賠償保険を始めとする7つの種類があります。
最近はその中から必要なものを組み合わせることができる「オーダーメイド型」保険が増えてきました。しかし、免許を取って間もない人や、保険の補償内容について「あまりよくわからない」という中高年世代にはやはり主な補償がセットになった「パッケージ型」が人気です。
すべてをカバーできるSAP
取り扱う会社によって多少の違いはありますが、おおむね「SAP」「PAP」「BAP」「ドライバー保険」の4つが主流です。このうち、7種類の任意保険がすべて入っているのがSAPで、対人・対物事故において示談交渉代行サービスが付加されているのが最大の特徴です。
対人にのみこのサービスが適用されるのがPAPで、BAPとドライバー保険にはありません。あくまで「サービス」なので、特約あるいは単独で契約しようとしてもできないことが多いようです。
いざという時に注意しなければならないことは?
自分が被害者で、しかもまったく過失がない場合などは、保険会社の示談代行サービスが使えないことがありますが、加害者であれば損害賠償額など、できるだけ少なくなるように交渉してくれますし、賠償金の支払い手続きまでしてくれますので、事故を起こしたら必ず連絡するようにしましょう。
SAPやPAPに双方が加入していれば、お互いの保険会社の示談担当者間での交渉となります。
間違っても、事故現場において当事者同士で連絡先を交換して終わり、などということをしてはいけません。警察に入ってもらい、実況見分調書や事故証明書を作成してもらわないと、後でトラブルになった時にどうしようもなくなります。
また、本来示談が成立した時には示談書を作成し、場合によっては公正証書にする必要もあるのです。
もしも自分が交通事故の被害者で、加害者側の示談代行担当者と交渉しなければならなくなった場合に、注意すべきはたった一つ、「安易に示談書にサインしない」ことです。
示談は一度成立してしまえば、不服申し立てができません。後から後遺症が出てきたり、やはり過失割合や賠償金額に不満を感じてもやり直しはできないのです。
そのためにも、少しでも加害者側の対応に納得のいかない点があれば(常識の範囲内で、ですが)、示談に応じてはいけません。
交渉の代行はしてくれなくても、保険会社の担当者は相談にのってくれたり、有益なアドバイスをくれたりしますので、そのためにも保険会社への連絡は大切なのです。
どうしても折り合いがつかない時は、交通事故紛争処理センターに和解の斡旋を依頼したり、交通事故の紛争解決を得意とする弁護士に相談するという手もあります。
保険会社によっては、担当者1人だけでなく、専門家によるチームサポート制を採用しているところもあります。その中には当然弁護士や事故調査士などがいますので、示談の際にスムーズに進む場合があるようです。
自分が加入しようとする自動車保険が「1事故1担当者制」「1事故専任チーム制」のどちらであるかはきちんと確認しておきましょう。
*ご参考にどうぞ「交通事故の示談交渉の実例~保険会社はどのように対応してくれる?」
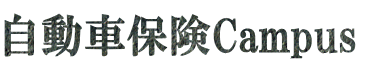
この記事へのコメントはありません。