
自動車保険の会社を変えると、せっかくそれまで無事故を続けて上げてきた等級がふりだしに戻ってしまうと思っている人もいるようですが、そんなことはありません。原則として、保険会社を変えても等級は継承できる仕組みになっていますので、安心してください。
ここでは、自動車保険の会社を変える際の等級について詳しく解説してみたいと思います。
会社間で情報共有されています
損保会社間では、前年度の契約状態を照合し合うことができる仕組みになっています。ある損保会社A社で加入していたプランをやめて、別の会社B社で契約する場合には、B社は前契約の等級などの情報をA社に確認ができるのです。
ただし、保険契約を継承する際に必要な情報に限られ、「補償金額がいくら」というような補償内容に関する情報は共有されません。
等級が継承されるというのは、「割増し」の場合も同じです。「1等級」や「2等級」など割り増しになっている契約者が他の会社で、新規契約の「6等級」からスタートしようとしても、できない仕組みになっています。
事故の有無の情報も共有されています。たとえば「10等級」の人が事故を起こしてしまい、翌年は「7等級」にダウンしてしまうのを回避するため、会社を変えて「11等級」で契約しようとしてもできません。
継承できるのは、満期日から7日以内
こうした等級継承のメリットが受けられるのは、満期日から7日以内と決められています。これは保険会社を変える変えないに関係なく、同一の会社でも8日以上過ぎると等級は継承できません。「満期日の翌日から起算して7日以内」という取り決めになっていますので、例えばその月の1日が満期日だった場合、8日までに継続手続きをしなければなりません。
なお「割り増し」については、7日が適用されません。1等級~5等級までの契約については、満期日を過ぎてもずっとその履歴は残されます。満期からしばらく間をあけて、他の会社で6等級の新規契約をしようとしてもできません。
共済には引き継げない?
等級の引継ぎは損保会社間では、全く問題なく継承できます。損保会社というのは、「○○海上火災保険」とか「△△火災海上保険」「○×自動車保険」「△○損保」などという社名の会社のことです。
損保ではありませんが、自動車保険を扱っている会社もあります。全労済、JA共済、全自共、教職員共済、トラック共済などの共済保険がそれです。共済については、必ずしも継承できるとは限りません。JA共済(自動車共済)や全労済(マイカー共済)は引き継げますが、それ以外の共済は引き継げない場合もあります。
共済から損保へ、損保から共済へ契約を変える場合には、あらかじめ継承できるかどうかを確認してから手続きを進めるとよいでしょう。
契約期間の途中でも会社を変えることはできます
保険会社を変えるのは、必ずしも満期のときだけしかできないわけではありません。何らかの事情で会社を変えたいときには、中途で変更も可能です。その場合、現在の等級がそのまま引き継がれることになります。無事故の場合、満期まで待って変更すれば1等級上がった等級で契約できますので、中途で変更するのは必ずしも得策ではありません。
保険会社によっては、2台以上の車を1証券にまとめて契約すると安くなる制度があります。A社、B社に分かれて加入しているのをA社にそろえて保険期間も同じにするため、B社からA社に乗り換えるというようなケースでは、使えるでしょう。
変更時には自動継続に注意!
一般的には、満期日に合わせて保険会社を変えることが多いです。その方が等級継承のメリットが大きくなりますし、手続き的にも面倒がありません。
ここで気を付けなければならないことは、「自動継続特約」「更新バックアップ」というような特約が附帯されている場合です。自分ではA社をやめてB社に切り替えたつもりでも、申し出をしない限り、A社側では自動的に継続手続きがなされてしまいます。保険会社を変える際には、自動継続になっていないかどうかを確認しましょう。もし、なっている場合には、更新しない旨を現在加入している会社に伝える必要があります。
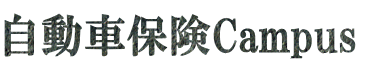
この記事へのコメントはありません。