
交通事故の後処理は、ほとんどの場合示談によって解決されています。損害賠償額や支払い方法などを当事者同士で話し合って決定します。成立すれば示談書にサインすることになります。
しかし、任意保険に加入していれば、保険会社の示談交渉担当者が契約者に代わって行うのが普通です。事故の記憶が生々しいうちに当事者同士が顔を合わせて冷静に話し合うということは難しいことがありますし、自分でできないことはないにしても、やはり自動車保険のプロに示談交渉してもらった方がスムーズに進むような気がしますよね。
衝突事故の具体例を見ていきましょう
優先道路を走行中に、脇道から出てきた車にぶつけられたMさんのケースです。
ある夕方、Mさんは、いつもどおり自宅までの県道を走っていたのですが、前の車と少し間が空いていたところへ、急に対向車線の車列の間からDさんの車が出てきました。
Mさんは時速30km程度のスピードしか出していなかったのですが、急ブレーキをかけても止まりきれず、ぶつかってしまいました。Dさんは県道より狭い脇道から出てきて、横断しようとしたのだそうですが、幸いにもケガはありませんでした。
Mさんは警察に知らせ、実況見分調書を作成してもらい、保険会社にも一報を入れました。
Mさんからの事故発生の知らせを受けた後、専任となった担当者が状況確認のためにMさんに連絡を取り、事故当時の詳細や車の損傷の程度をヒアリングした上で解決までの流れを説明します。次に、担当者はDさんへ連絡を取って了解を得てからDさんの加入している保険会社の担当者へ知らせます。
Dさんが保険会社に報告した内容が、Mさんとほぼ一致することを確認できたら、お互いに相手方の車の修理にかかる費用を調査することになります。その結果を基に、過失割合(責任割合とも言います)についての話し合いをすることとしました。
過去の事例等から導き出される過失割合
過失割合(責任割合)はMさん10%、Dさん90%となりました。Dさんの前方不注意や、狭い道から優先道路へ出てなおかつ横断しようとしたことなどが考慮されています。
Mさんには修理代として、Dさんからの賠償金と、車両保険から不足分が支払われました。一方、Dさんは対物賠償保険金から過失相殺された額を受け取ることになります。
双方の車が動いていた場合、よく言われることですが100対0にはなりません。確かにMさんの走行していたのは優先道路ですが、まったく責任がないということにはならないのです。この本件は、過去の事例等を参考とした上で、「Mさん10%、Dさん90%」の過失割合(責任割合)で示談が成立しました。
ちなみに、示談とは、「これだけの支払いを以て賠償は完了したものとする」と言うことであり、示談書にサインした後は取り消しや再度の賠償金請求はできないので注意が必要です。
結果に納得がいかない時はサインしない
こうした経過については、保険会社の担当者から随時報告がありますので、不満や納得がいかないことがあればその都度伝えるようにしましょう。また、ケガを負い、その治療が継続している間(医師にまだ治癒もしくは症状固定を言い渡されていない)は示談に入らないようにしましょう。
特に、自分が被害者で、加害者が刑事責任に問われている場合、示談が成立していると刑が軽減されて起訴猶予となったり、本裁判に入っていても情状酌量・執行猶予となるため、示談を急ぐことがあります。
このような背景があるとしても、安易に示談書にサインをしてはいけません。重ねて言いますが、示談が成立してしまったらもう覆しようがないのです。
どうにも話がまとまらなければ、交通事故紛争処理センターや日弁連事故相談センターに相談してみる手もあります。示談交渉に強い弁護士が常駐していますので、有益な助言をもらえるでしょう。
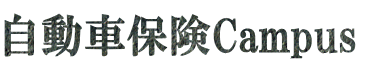
この記事へのコメントはありません。