
自動車保険を選ぶときには、将来の掛け金がどうなるのかも知っておくべきです。火災保険などと異なり、自動車保険の場合は毎年掛け金が変わります。「等級制度」という仕組みがあり、事故を起こさなければ年々掛け金が安くなるようになっています。
ここでは、具体的に等級制度の仕組みについて解説してみたいと思います。
個人契約に多いノンフリートとは?
自動車保険の料率は、大きな会社などで10台以上車を持っている契約者の場合、10台未満の契約者とでは仕組みが異なります。10台以上の保有者に対する料率制度を「フリート」と呼び、10台未満を「ノンフリート」と呼んでいます。
普通の個人が10台以上保有していることはまれなので、ここでは「ノンフリート等級制度」についてご案内します。
等級による割引の仕組み
「ノンフリート等級制度」は、1等級から20等級まで細分化され、「等級」は契約者ごとにランク付けされています。数字が大きければ大きいほど「お得」になる体系です。はじめて自動車保険に加入する場合には、「6等級」からスタートします。
1年の加入期間中に一度も保険金を請求しなければ、翌年度は「7等級」にあがります。たとえ事故を起しても「請求」さえしなければ上がります。7等級にあがると保険料は前年度よりもおよそ1割安くなります。翌年も無事故なら8等級となり、さらに1割安くなります。
安くなる割合は会社によって異なり、9等級以上になると数パーセントずつ安くなっていく仕組みです。最高ランクの「20等級」まであがると、掛け金は6割ほど割安になります。
事故を起せば掛け金は高くなります
1年間、無事故で保険金を請求しなければ、翌年には等級がひとつアップし掛け金が安くなりますが、事故を起して請求をした場合には等級はさがります。この場合、翌年には最大で3等級ダウンとなります。
ただし、火事・台風・盗難など運転中の事故以外の理由で車両に生じた損害で保険金を受け取った場合には、1等級のダウンのみで済みます。また、弁護士費用特約などだけを使った場合には、事故としてはカウントせず等級ダウンはありません。
会社を変えても引き継がれます
この等級制度は、全損保会社共通のデータベースで管理されているため、加入する会社を移動しても引き継がれる仕組みになっています。8等級の人が満期時に他の会社で契約すれば、9等級からスタートできます。
事故を起こして翌年は等級がさがるからと、よその保険会社で契約しても残念ながらそのまま等級は継承されます。掛け金ののアップを避けることはできません。等級制度の引継ぎは損保会社だけでなく、マイカー共済やJA共済などでも同様の対応です。掛け金の比較をする際には、各社に現状の等級を伝えて見積もりしてもらうことになります。
事故ありと事故なしでは割引率が異なります
かつては、等級が同じであれば割引率も同じでしたが、2012年の等級制度の改定で事故のあるなしによって、割引率が分けられるようになりました。
例えば、20等級の人が事故を起こして17等級に落ちた場合と、16等級の人が事故なしで17等級に上がった場合には、同じ17等級でも2割前後の差が生じます。事故なしであがった人の方が安くなるのです。
こうした格差は事故を起こした翌年から3年間続きます。3年間事故を起こさなければ、事故なしの人の割引率に追いつくことができます。
自動車保険の等級制度が、事故をした人に不利になっているのは、一度事故をした人というのはまた事故をするリスクが高いからです。
掛け金が高くなるからといって、保険を継続するのをやめてしまうのは危険です。自動車事故の賠償金は、場合によっては数億円になってしまうケースもあります。個人の支払能力をはるかに超える金額になりますので、車を運転するなら必ず入っておくようにしましょう。
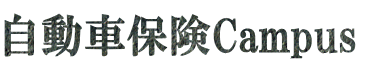
この記事へのコメントはありません。