
自動車保険の仕組みががよくわからない、という人は少なくありません。じつは保険商品の中でも、自動車保険は一番複雑な商品なのです。そのため、損保を取り扱う仕事をしている人の中にも苦手意識を持っている人は少なくありません。ややこしい仕組みがあったり、法律的用語が登場するなどことばがわかりづらかったりという面があるからでしょう。
難しいからといって、なにもわからないまま契約することはできませんので、その仕組みについて概要をご案内します。
自賠責と任意保険の違い
仕組みをややこしくしている理由の一つが、自賠責と任意保険とがあることでしょう。自賠責は法律によって加入が義務付けられていることから「強制保険」とも呼ばれます。
補償しているのは対人賠償のみ、つまり人に対してケガをさせたり死亡させてしまったときの保険です。車に対する修理代などは対象外です。補償される限度額は死亡事故の場合で3000万円です。
死亡事故を起こした時の最低限の補償をするのが自賠責となります。一般に死亡事故を起こしたときの賠償額は3000万円ではおさまりません。
高額なケースでは3億円以上となることもあります。任意保険では自賠責で賠償しきれない部分を支払います。通常は補償の限度額が「無制限」となっており、賠償金額がいくらになっても保険でカバーできるようにしてあります。
詳しい補償内容を見ていきましょう
任意保険では、対人賠償以外の事故についてもカバーしています。物を壊したときの「対物賠償」、自分の車に乗せている人のための「人身傷害」や「搭乗者傷害」、自分の車の修理代をまかなう「車両保険」などです。
車同士ではなく単独で起こした事故、たとえば電柱にぶつけてしまったというような事故で、自分自身や同乗者のケガや死亡は「自損事故保険」でカバーされます。これは、対人賠償に加入していれば自動的に付帯される仕組みになっています。
基本的な制度を知ろう
自動車保険の料金のベースとなるのは、車の種類、運転者の免許証の色、運転者の年齢、「ノンフリート等級」などです。軽自動車と普通自動車とでは保険料がことなりますし、運転者がゴールド免許のときには割引が適用されます。逆に年齢の若い人が運転する場合には高くなる仕組みになっています。
ノンフリート等級とは、運転者ごとに割り振られるランクのようなもので、はじめて保険に加入するときには「6等級」からスタートします。
その年度に事故を起こさなければ翌年は7等級に、さらに翌年は8等級へと毎年アップしていき、等級があがればあがるほど掛け金は安くなる仕組みです。逆に事故を起こすと、3等級ダウンし掛け金は高くなります。
要するに優良なドライバーほど安く加入できる仕組みとなっているわけです。
運転者を限定すると安くなる
自分の同居の家族以外は運転しない自動車であれば「家族限定」にすると、掛け金は安くなります。「家族限定」には、本人と配偶者だけに限定するものと、同居の家族に限定するものとがあります。
運転する人の年齢によっても安くなります。保険会社によってもことなりますが、何才の方でも運転できる「全年齢補償」、21才以上の方しか運転しないと限定する「21才以上補償」のほか、「26才以上補償」「35才以上補償」などがあります。家族の中で、自動車を運転する最も若い方の年齢に合わせて選ぶことになります。
使用目的でも変わります
自家用車を日常生活やレジャーにしか使わない場合、通勤や通学にも使う場合、仕事にも使う場合で、掛け金がことなります。レジャー目的にしか使用しないケースが最も安くなる仕組みになっています。
自動車保険は補償内容のほか、運転者の限定や年齢条件、ノンフリート等級などによって保険料が決まる仕組みです。契約時に不利にならないように、覚えておきましょう。
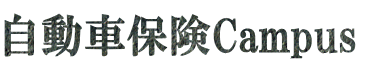
この記事へのコメントはありません。