
自動車保険料は、おなじ車でも使用目的が違えば保険料がことなる仕組みになっています。毎日乗る人と、たまにしか乗らない人では事故を起こす機会もリスクもことなりますので、あまり乗らない人には安く、頻繁に乗る人には高くという設定になっているのです。
ここでは車の使用目的によって具体的にはどのような違いがあるのかについて詳しく見ていきましょう。
使い道は3パターンに分かれます
自動車保険に加入する際にたずねられる車の使用目的は、ほとんどの会社で次の3つから選択するようになっています。
ひとつは、日常・レジャーです。平日にはあまり乗ることがなく使用目的がもっぱらレジャー等に限られ、週末や休日に買い物やドライブ、旅行などに使う場合。多くの方がこのカテゴリーに入るでしょう。
二つめの使用目的は、通勤通学です。日常生活での使用に加えて、通勤や通学などでもお使いになられる場合です。自分で運転しなくても、毎日奥さんが駅まで送り迎えするようなケースや、お子さんを送り迎えするのも含まれます。
三つめの使用目的は業務です。飲食店や小売店が配達用に使用するなど、自分の仕事の中で車を使用するケースです。ただし、運搬そのものが事業であるもの、たとえば宅配業や運送業はこれには該当しません。別形態となります。
通勤通学の定義は?
通勤通学用の場合、年間を通じて平均して月に15日以上、その目的のために使用する場合です。通学の定義は保険会社によっても若干違いがありますが、幼稚園や小・中・高校、大学、養護学校などの学校教育法にさだめられた学校に通う場合です。都道府県知事の認可を受けた予備校や専門学校なども含みます。
通学といっても、必ずしも学校までの送迎・通学ではなく、最寄り駅までの送迎も含まれます。毎日子どもを駅まで送っているのであれば通学です。雨天などにたまに送るだけなら通学にはならず、日常・レジャーとみなされます。
業務の定義は?
業務の使用目的の定義は、年間を通じて平均して月に15日以上、仕事に使う場合です。業務とはそれによって収入(対価)を得るものを指しますので、ボランティアとして働くものは含みません、
告知した内容とことなる使用をした場合はどうなる?
使用目的はあらかじめ加入時に保険会社に告知しますが、一般的には告知以外の目的に使用すると保険金が下りなくなるということはありません。日常・レジャーを選んでいる人が、たまに通勤にも使用したというケースは大丈夫です。
ただし、契約当初は日常・レジャーにしか使用しなかった方が、事情が変わって通勤通学に使用するようになった場合などには、使用目的の再告知が必要です。その場合、保険料が変わります。
告知義務違反なら支払い拒否もあり得る
使用目的によって車の保険料はちがってきます。業務がもっとも高く、次いで通勤・通学、一番安いのが日常・レジャーです。
安いからといって、本当は業務に使用しているのに日常・レジャーで申し込むと、実際に事故を起こした際に支払いを拒否されてしまうケースがあり得ますので、虚偽の使用目的で申告はしてはいけません。
なお、業務に使用として告知した人が業務使用をやめて通勤・通学や日常・レジャーに変わったことを告知しなくても、告知違反を問われることはありません。また、通勤・通学の告知の人が、日常・レジャーに変わった場合も同様です。
掛け金が高い方から低い方への変更は告知しなくても許されます。逆に、低い方から高い方への変更を告知しないでいると、悪意があると判断されてしまうケースがあり得ますので、気を付けましょう。
自動車保険は万が一の場合に備えるものですので、大事なときに使えないのでは意味がありません。掛け金の安さに魅かれて告知義務違反をすると、結果として大きな損失をこうむることになりかねませんので、使用目的の虚偽申告はやめましょう。
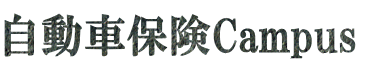
この記事へのコメントはありません。