
2013年は大手損保会社が相次いで自動車保険料の値上げやノンフリート等級制度の改訂などを行いました。
こうした値上げのおもな要因は「損害率の上昇」です。損害率とは、その年度に会社が受け取った保険料の総合計と、支払ったお金との比率です。かつては50%台が普通でしたが、最近は70%台まで上昇しています。
つまり、1000億円の保険料収入があったときに、以前なら500億円近くが会社に残ったのに、最近は300億円程度しか残らなくなったということです。
収益にダイレクトに大きなインパクトを与える損害率の上昇は、損保会社にとっては大きな問題です。損害率の改善は損保にとって近々の重大なテーマとも言えます。
損害率の上昇は、高齢ドライバーの急増と若年層の車離れによるものと言われています。その内容を詳しく見てみましょう。
損害率7割では損保はやっていけない!?
自動車保険の値上げの主な要因は損害率の上昇です。1980年代には50%台だった損害率が2000年代に入り60%を超え、毎年のように上がり続けました。2009年度にはついに70%を超えてしまいます。
損害率とは、支払った保険金と損害調査に要したコストの合計と、収入との割合で、損保会社の収益のバランスを表すものです。損害率が悪い(高い)会社ほど収益率が低く、経営バランスが悪いということになります。
かつて損害率が50%台だったころですら「自動車保険は収益性がよくない」といわれていました。損保にとって、損害率は5割以下が望ましかったのです。それが、今では7割前後にまで達してしまいました。これでは会社はなりたちません。
自動車保険は損保にとって収益の柱です。売上にかなりおおきなウェイトを占めますので、この分野で利益があがらないと事業経営上大きなマイナスとなります。
損害率改善の方法は掛け金アップしかない!?
事故を起こすのは契約者です。損害保険会社は損害率をコントロールできません。起こった事故に対しては保険金を支払うのは義務のため、事故が起これば支払わなければなりません。
支払うお金の額は会社サイドでは動かせないため、損害率を改善するには、分母になる掛け金の部分をおおきくするしかありません。そのために、値上げという形をとったわけです。
高齢ドライバーの増加が一つの要因
損害率が上昇する一つのおおきな要因は、高齢者がふえたことです。昭和20年代始めに生まれた「団塊世代」が65歳を超え高齢者の仲間入りをはじめました。人口の最も大きな塊が一気に高齢者集団になってきたわけです。
団塊世代は昭和40年代のモータリゼーションを支えた人たちですので、自動車免許の保有率も自動車の保有率もとても高い世代です。この塊が高齢となり、事故を起こしやすいグループに入ってきたことで、ますます損害率を上昇させる要因となっています。
若者が乗らないことも大きな要因
最近の若者は車を所有しなくなりました。そのため、若い人たちの自動車保険加入が減り、損保会社の減収につながっています。
総務省の調査によれば30歳未満の独身者の自動車保有率は、最近10年間で17%近くもダウンしました。これは、この世代の自動車保険の加入件数減にダイレクトにつながります。
損害率の分母である「収入保険料」は当該年度に入ってきたお金ですが、これは将来支払う保険金のためのもの。これに対して、分子である「支払い保険金」は過去に受け取った掛け金に対する支払いです。
実は分母と分子はタイミングが少しずれているのです。分母がどんどん増えていく局面においてはあまり問題になりませんが、減少する局面になると大きな問題です。
若者がクルマに乗らず将来にわたって分母が小さくなっていき、高齢者の事故増加などにより分子が増えていくと、会社の収益は急激に悪化します。保険会社が、つぎつぎと値上げをせざるを得なくなっているのは、こうした背景があるからです。
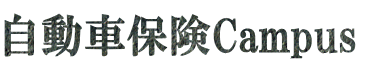
この記事へのコメントはありません。